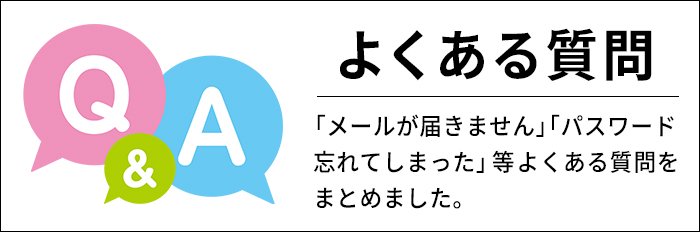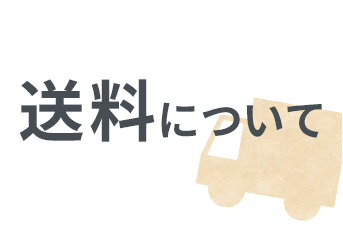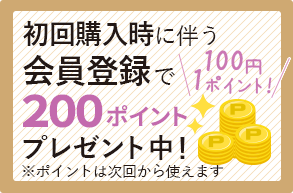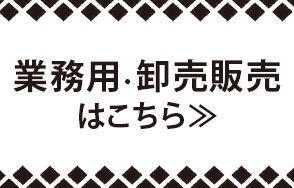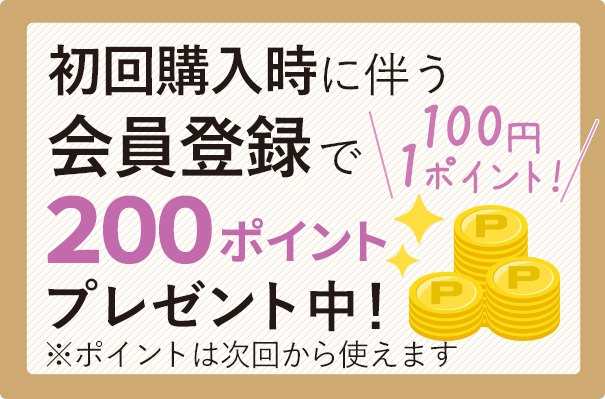米澤製油さんを訪ねて〜国産100%なたね油を知る〜

豆庵の「厚あげ」や「絹ごしがんも」の揚油、「豆腐のマヨ」や「糀生ドレッシング」などには米澤製油さんの国産なたね油を使用しています。
米澤製油さんは埼玉県熊谷市で明治二十五年よりなたね油一筋にやってきた老舗製油会社です。かつて菜種は搾れば行灯や食用に、搾りかすは畑の肥料にと日本人の暮らしに必要不可欠だったことから全国で栽培されていました。高度経済成長期に国産菜種は生産量のピークを迎えましたが、その後輸入自由化により海外産が安く国内に入ることになり、現在では国内で流通する菜種の内、国産は僅か0.15%と激減し、大半は輸入に頼っているのが現在の状況です。その輸入菜種の約90%は遺伝子組換えと言われていますが、米澤製油さんは「安全が確認できないものは使わない」信念のもと、海外産菜種でも遺伝子組換えのものは使用せずに分別管理されたものに限定しています。また食料自給率向上のため、希少な国産菜種を積極的に使用することで菜種生産者を支援し国産の普及に長年に渡り尽力されています。

原料となる国産菜種
一般的な食用油には、製造過程の間に一括表示からは見えない加工助剤が使われています。製品に成分が残らないので表示義務はありませんが、米澤製油さんではこのような化学薬品も使わずに油を製造しています。生産効率は悪くなりますが、ヘキサンを使わずに圧力のみで油を搾り、リン酸や苛性ソーダを使わずにお湯で油を何度も洗う独自に開発した「湯洗い洗浄法」で精製することで臭いやえぐみのない使いやすいサラダ油に仕上げています。製油後のシリコーン(消泡剤)やトコフェロール酸(酸化防止剤)の添加も行なっていません。
今回、そのような食べる消費者の安全と安心を考え油を生産している米澤製油さんの工場を見学させていただきました。
すでに敷地内に入った時からほのかに香ばしい香りが漂っていましたが、工場に入ると、近くに菜種の焙煎炉があったためか、さらに濃厚な菜種の香りに包まれました。おそらく、菜種の香ばしい香りを嗅いだのは初めてで、胡麻とも違う芳しい香りに癒されました。
 炉で焙煎すると青臭さが取れ香味がつきます。
炉で焙煎すると青臭さが取れ香味がつきます。 レンガ製の焙煎炉は昨年まで現役だったそう。
レンガ製の焙煎炉は昨年まで現役だったそう。
圧搾からゆっくり搾り出された油は深い緑色を帯びており、圧搾したての菜種油を試飲させていただきました。菜種独特の香りが口にほのかに広がりこれはこれで美味しい!この時点でも口当たりの良い印象でしたが、社長曰く「湯洗いした後の油も飲んでもらうけど、これに比べたら水みたいだよ!」とのこと。
 圧ぺんといってローラーで潰し油を搾りやすくする。
圧ぺんといってローラーで潰し油を搾りやすくする。 少し油が出てきている。
少し油が出てきている。

ヘキサンなどは使わずに圧をかけてゆっくり搾り出していく
搾りかすも見せていただきましたが、サラサラした砂のようでした。一般的なサラダ油の製造工程では、歩留を良くするために「二番搾り」といって最初に搾った粕からヘキサンでさらに油を抽出しますが、米澤製油さんはそれはしません。ですので、米澤製油さんは少し油分の多い菜種油粕を飼料や有機肥料用に販売しています。

搾りかす
そして、気になっていた湯洗い洗浄の工程へ。油とお湯を遠心分離器に6回かけて不純物を除きます。回数ごとに油の色を見ることができるのですが、回を重ねることに油の色が透明に変化していくのを見て驚きました。

湯洗い洗浄した後、脱色・脱臭をしてろ過することで透明感のあるサラダ油に。
ここで湯洗い洗浄し不純物が取り除かれた油を試飲させていただくことに。
口に入れた感じが軽く、社長がおっしゃっていたようにお水のようでした。
社長が「町内のイベントでかき揚げに使う油をうちのに変えたら、胃もたれしないし揚げててもベタベタしないと喜ばれた。」と満面の笑みで話してくださいました。
その気持ち、実際使っているので納得です!
工場見学させていただき、小さな種から製油するまでの多くの工程が食べる消費者の安全と安心を第一に考えられたもので、美味しさの裏側には理由があると改めて感じました。
また、印象に残ったことは、産業廃棄物となるものはほとんどと言っていいほど残っていないということでした。
精製過程で丁寧に取り除かれた濁り成分や、脱臭・脱色後に出る不要な脂肪酸は、バイオ燃料などに再利用しているとのことです。油の搾りかすは菜種油粕として有機肥料や鶏のえさに活用しています。菜種を最後まで大切に使われていることに感動しました。

工場の一画にある菜種畑は、従業員さんたちが栽培している。
なたね油のよいところ
油は複数の脂肪酸によって構成されています。よく耳にする脂肪酸としてはオレイン酸、リノール酸、リノレン酸、中鎖脂肪酸です。どの脂肪酸も人の体にとっては有効で、望ましい摂取割合があります。なたね油は、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸が理想的な摂取割合で入っており、植物油のなかで最もバランスの取れた油と言えます。
米澤製油さんの3つのこだわり
1.非遺伝子組み換え原料菜種を使用しています。
日本では、なたね油の原料となる菜種のほとんどはカナダやオーストラリアから輸入しています。しかし、その90%は遺伝子組み換え(GM)菜種です。遺伝子組み換えについては、いまだに100%安全だとは言い切れません。「安全が確認できないものは使わない」という信念のもと、当社が使用する原料菜種は、すべて産地を指定し、栽培・流通の各段階で分別していること(IPハンドリング)が証明されたものだけを使用しています。
2.国産自給率向上を目指し、産地拡大に努めています。
国産菜種の生産量は年間3,000tを超えるまで回復しました。栽培に手間がかからず、菜種を植えたあとの畑では他の作物の生育が良くなったり、収量が上がったりする有用な作物です。しかし、その使い道がなければ生産量は増えていきません。当社では国産菜種の生産量の約7割(2,250t)を購入し搾油することで、農家の方々を買い支え、自給率向上に努めています。
3.製造工程において化学合成薬品・食品添加物は使いません。
一般的なサラダ油は、圧搾法と抽出法を併用して搾油します。抽出法ではノルマルヘキサン(石油関連製品)が使われ、圧搾後の原料に残った油分を極限まで溶かし出します。また、精製工程では、リン酸、シュウ酸、苛性ソーダ、活性白土を使用して効率良く精製します。当社では、圧搾法のみで搾油し、精製工程では油にお湯を混ぜて何回も洗う「湯洗い洗浄法(特許製法)」で精製し、製品へのシリコーン(消泡剤)の添加も行っていません。

米澤製油さんの商品はこちら
米澤製油さんの油を使った商品はこちら



 新商品・新入荷
新商品・新入荷